浅草が「履物の街」になった歴史
花川戸の誕生
「花川戸」は東武浅草駅の北側、隅田川沿いの一帯。
隅田川と並行に走る江戸通りと馬道通り、言問通りに囲まれた三角形の地域です。
20年程前まで江戸通りには和装履物問屋が並んでいましたが、現在はその数もかなり減り、靴のメーカーが目立ちます。
江戸初期寛文11年版の寛永図にはすでに「ハナ川戸丁」と書かれています。
当時の物流はが水運が主流だったので、隅田川沿いの地の利もあって、早くから開けていました。
「花川戸」という名前の由来は、徳川八代将軍吉宗が川沿いに植樹した桜並木が「墨堤の桜」として親しまれたことによるそうです。
隅田川の渡し舟の一つ「山の宿の渡し」で、人々は花川戸と対岸の墨堤を行き来していたことでしょう。
江戸末期、浅草寺の子院である寺社、商店、民家が建ち並んでいた花川戸は、江戸っ子の憧れるヒーロー「花川戸助六」と「幡随院長兵衛」を輩出しています。

芝居小屋「猿若三座」の隆盛とともに
天保13年(1842)~明治5年(1872)の約30年間、花川戸の北部、猿若町には幕府公認の芝居小屋、「中村座」「市村座」「森田座」の猿若三座が繁栄を極めていました。
この界隈に役者や芝居関係者が多く住んでいた影響もあってか、明治初期の花川戸に鼻緒の職人が集まったようです。


また、栃木から鼻緒に使う麻紐が舟で運ばれて来て花川戸で荷を下ろしたことも、鼻緒製造の仕事が多かった理由であると思われます。
現在も花川戸から浅草6、7丁目には鼻緒の製造職が点在していますが、看板など出していない家内工業なので、普通のしもた屋にしか見えません。
明治20年頃から下駄、下駄表、実用草履、爪皮などの卸店がひらけて、明治27~28年の日清戦争後の好景気をきっかけに、問屋街が形成されました。
和装から洋装へ
大正3年、第一次世界大戦が始まり、ロシアから大量の軍需向け皮革製品の注文が入ったことで、下請けを担った浅草北部地区の中小靴工場が活況を呈します。
この頃から、ゴム、キルク、フェルト等が日本に大量に輸入され、花川戸の履物業界もこれら新素材を取り入れて発展しました。
大正モダニズムで洋服を着る人が増え、さらに関東大震災を契機に生活様式が大きく変わり、靴の需要も激増。
震災による大打撃は受けたものの、東京市の復興とともに浅草・花川戸も転換期を迎えます。
昭和初期、花川戸の履物問屋街は最盛期を迎え、草履・下駄・鼻緒など和装履物関連の問屋が250軒、周辺の関連業者を合わせると800軒にも達したといいます。
また日常の履物が下駄から靴へ移りつつあり、安価な布製ゴム底靴の需要が多くなると、関連する業者も増加しました。

戦後の活況とバブル崩壊
昭和6年、満州事変を契機として軍需品の発注を受けた皮革産業は躍進するものの、昭和16年に太平洋戦争が始まり、戦時中は物資や労働力の不足により業界は衰退。
昭和20年の東京大空襲によって、東京下町一帯は焦土と化し、浅草および花川戸も焼け野原となりました。
戦後の復興後、昭和25年に朝鮮戦争の特需景気で花川戸の問屋街も活況を取り戻し、このころケミカルシューズなどゴム底の靴やサンダル、スリッパなどをはじめ、傘、ハンドバッグなど商品も多様化します。
昭和30~40年代の高度成長期には、高級呉服が飛ぶように売れたことに追随して和装履物業界も好景気を迎えることとなります。
しかしながら平成に入ると安価な中国製品におされ、花川戸のメーカー・問屋も少なくなり、バブル崩壊後はさらに加速。現在の花川戸はマンションの方が目立つようになってきました。
参考資料:『花川戸今昔』(花川戸経営研究会)

和装履物の業界は
呉服業界の縮小とともに、和装履物関連のメーカーや問屋も廃業が相次ぐようになります。
現在も花川戸から馬道にかけて、鼻緒および草履製造の職人やメーカーは残っていますが、業界全体の高齢化・後継者不足には歯止めがかからない状況です。
辻屋本店では、先代までの取引先だった卸問屋が辞めてしまったり、また呉服業界と同じく流通が少しずつ変化していることから、現在は職人や製造メーカーに直接注文し、一点一点こだわった商品づくりを行っております。
問屋を経由しなくなったことで価格を抑え、お客さまのご要望を細やかに反映させることができるようになりました。
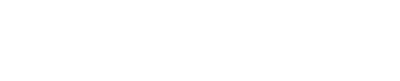
コメント
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。