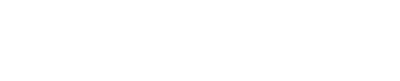浅草と辻屋本店のあゆみ

辻屋本店 伝法院通りにあった店舗 (2024年10月より花川戸の仮店舗にて営業中)
大正元年 辻屋本店の創業
大正元年、本所石原町三丁目(現在墨田区石原)で、初代・辻 巳之吉(みのきち)が下駄屋を開業したのが、辻屋本店の創業です。巳之吉の先代は、メリヤスを商っていたらしいのですが、当時は「糸ヘンの商売(繊維関係)は相場が激しい」時代で、父親が幾度も大変な目に会ったのを見ていたのかもしれません。
大正12年の関東大震災は浅草にも大打撃を与え、壊滅に近い状態にまでなってしまいます。浅草のシンボル凌雲閣(別名十二階)も姿を消しました。
その後、浅草はたくましく復興し、震災前は区役所通り(現在のオレンジ通り)までだった新仲見世が、六区までつながりました。
本所を焼け出された巳之吉は、その場所に新しく和装履物店、辻屋を出します。

新仲見世商店街にあった頃の店舗
娯楽の中心、浅草

仲見世の入口、言わずと知れた雷門
当時の浅草六区はまさに、東京の娯楽の中心地。流行の最先端の町だったといいます。
昭和4年には六区電気館にて、日本で始めての本格的トーキー映画の上映。そしてエノケンがカジノ・フォーリーを創設。古川緑波の軽演劇と共に、エノケン・ロッパの時代が訪れます。浅草の黄金期です。
しかし昭和16年に日本は太平洋戦争に突入し、時代は徐々に陰りを帯び、昭和20年の東京大空襲で、下町はほとんど焼失してしまいます。浅草もほぼ全滅状態でした。
映画全盛の頃
戦後の焼け跡に二代目・辻 政(ただし)は、物資の不足するなか、必死で店を再建します。昭和20年頃は統制経済の下、下駄も配給だったといいます。
ましてや革草履など贅沢品は手に入らず、「絹エナ(メル)草履」というのがあったそうです。「綿に塗料が塗ってある草履で、色落ちが激しいから白い足袋がすぐ染まった」とは政の次男、辻 毅政の話。
昭和30年頃より日本が元気を取り戻すにつれ、浅草にも活気が戻ってきます。なんといっても映画全盛期、映画館が軒を連ねる六区は連日連夜の賑わいだったそうです。
平日でも映画がはねた夜の10時頃、新仲見世を歩くと、人の頭で向こうが見えないほどだったとか。
映画の他にも、女剣劇(大江美智子、不二洋子、浅香光代ら)が大流行、松竹歌劇団(SKD)が大ブームを呼び、さらにストリップ劇場からは渥美清やコント55号などのコメディアンが多数生まれます。
「この頃は今でいえば、歌舞伎町のような感じだったかな。当時はキャバレーが流行っていて、ホステスの女の子がお客さんをつれて草履や下駄を買いにきてくれたもんだ。」(辻 毅政 談)
テレビの時代
30年代半ばからテレビが普及し始め、39年の東京オリンピックでほとんどの家庭がテレビを持つようになると、六区の映画館へ足を運ぶ人も減り、浅草も変化せざるを得なくなります。
昭和57年には国際劇場がSKDの第51回東京踊りを最後に廃業し、跡地には浅草ビューホテルが建ち、松竹演芸場の跡地にはROXビルが建てられました。
和装履物も生活の洋風化に伴い、需要が減っていくことになります。今では想像するのが難しいけれども、昭和30年ごろまでは、靴を履くのは特別なことで、下駄や草履が当たり前でした。
変わりゆく浅草、そして変わらぬ浅草
娯楽の中心としての位置からは退いてしまった浅草ですが、街の魅力は今もなくなってはいません。
雷門から仲見世通りをひやかしながら、ぶらぶら歩いて観音様でお参りして、六区で寄席に入った後は、新仲見世通りで買い物、帰りにおいしいものでも食べて帰ろう、こんなまるでテーマパークみたいな楽しみ方ができるのは、浅草ならではだと思います。
家族で代々商っている店が多いので、昔と変わらぬ安心感があるのでしょう、お年寄りはもちろん、若い人も「浅草に来るとほっとする」と言います。天ぷらやトンカツ、洋食など庶民の味が手頃な値段でおいしいのも、魅力の一つです。お金さえ出せば、世界中の料理が食べられる時代ですが、普通の食べ物が安くておいしいのは、大事なことですよね。
和装履物の商いについて言えば、下駄や草履を履く習慣は次第に遠くなってしまいましたが、同時にその良さも見直されています。
平成の中頃から、夏の花火大会などでの浴衣姿は当たり前の風景となりました。
着物もまた、外出時の選択肢のひとつとして楽しむ人が徐々に増えつつあります。
一方で、辻屋本店のような和装履物専門店はどんどん廃業しているのも現実。
私共は「和装履物は挿げ次第」を信条とし、これからも履き良くお洒落な草履や下駄をご提供してまいりたいと思っております。